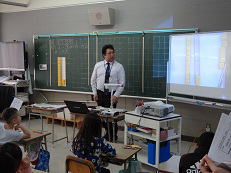~だれもが「わかる」「できる」算数科の授業づくりを通して~
ことができるであろう。
を育てることができるであろう。
ーションを図りながら、学び合い高め合う力を育てることができるであろう。

〇学習内容の定着を図るための指導過程のあり方
①本時の目標に応じた授業づくり
②「わかった」から「できた」を実感させる振り返り場面の工夫
③授業と連動させた家庭学習の指導
〇自分の考えを持ち、筋道を立ててわかりやすく表現するためのノート指導のあり方
①ノートの基本の型の指導
②ノートづくりを意識した板書構成の工夫
③図、表、文字などによる自力解決
④ICT機器の活用
〇多様な発想を引き出し、自分の考えを深めたり、広げたりすることができる話し合いのあり方
①1分間スピーチの活用
②ペア・グループでの話し合い活動
③算数的表現方法を用いた問題解決
④話し合い活動の工夫
⑤ICT機器の活用

①学習規律の確立
②黒板前の整理、整理整頓された教室環境
③クラスのルールの視覚化
④教室掲示(単元の流れ 既習事項 家庭学習)
⑤家庭学習の習慣化
⑥書く力の育成
⑦話す力・聞く力の育成
②全校的なコミュニケーションの力を育む取組
③支持的風土のある学級づくり
④保護者への研究内容の情報提供